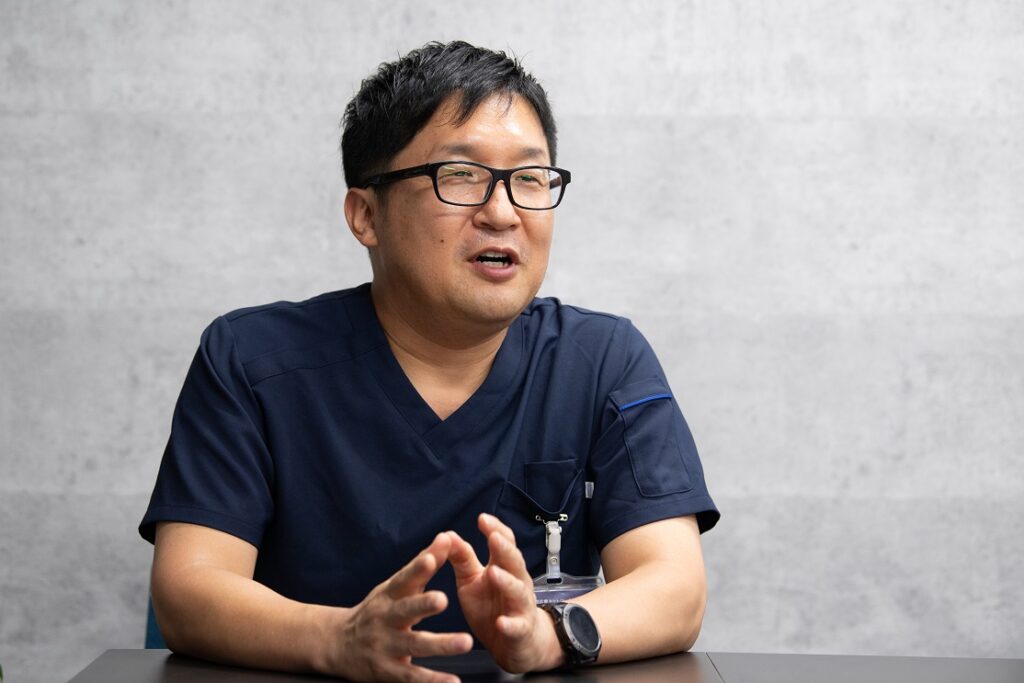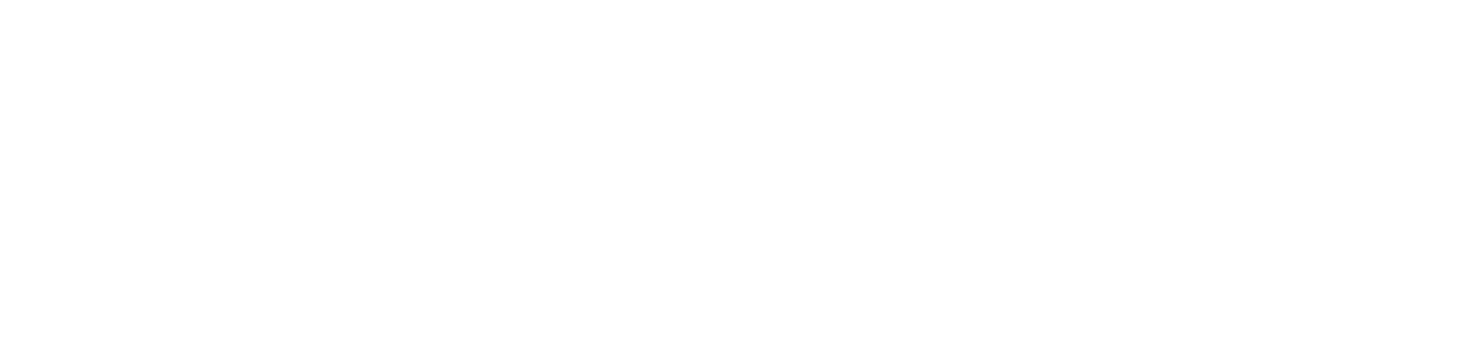理事長メッセージ
理事長ごあいさつ
皆様、こんにちは。さいたま北クリニック理事長の山岡啓信と申します。
健康でいられることは、幸せなことです。しかし誰だって病気を患い、その病気で自分の生活や家族の生活に影響が出てしまうこともあります。
大切なのは人生を楽しむことです。私は、医師として自分のできる限り皆さんの人生に寄り添っていきたいと思います。
当院では、皆様の健康と生活の質を最優先に考え、訪問診療サービスを提供しております。
訪問診療は、病院やクリニックへの通院が難しい方々にとって、医療を身近に感じていただける大切な手段です。
私たちは、医療の専門知識を活かし、高度な医療機器を使用した診断や、慢性疾患や難治性疾患の専門的な治療が可能です。
例えば、糖尿病や心不全、呼吸器疾患などの管理も行われます。
また、がん患者など、終末期のケアが必要な方には、痛みの管理や精神的なサポートを含む在宅緩和ケアが提供されます。
この分野では、医師、看護師、メディカルサポーターが連携して、
患者とその家族のQOL(生活の質)を維持・向上させることを目指します。
患者様だけではなく、患者様のご家族とも密接に連携し、安心していただけるようなサポート体制を整えております。
さいたま北クリニックは、訪問診療を通じて、皆様の健康管理をお手伝いし、安心して暮らせる日々をお届け致します。
どうぞ、ご不安なことやお困りごとがございましたら、いつでもご相談ください。
これからも皆様の信頼に応えられるよう、スタッフ一同、全力を尽くしてまいります。
医療法人社団 三世会 さいたま北クリニック
理事長 山岡啓信
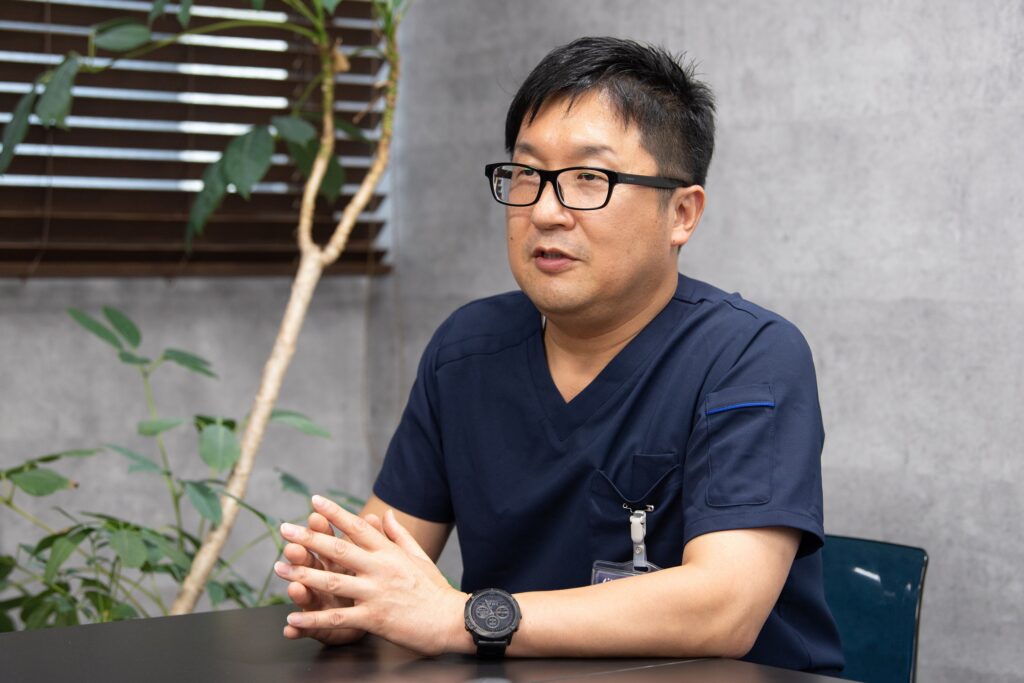
経歴
- 2002年 島根医科大学医学部卒業
- 島根医科大学第一外科
- 公立宍粟総合病院外科
- 手稲渓仁会病院心臓血管外科
- 順天堂大学心臓血管外科
- 小張総合病院心臓血管外科
- 戸田中央総合病院心臓血管外科
- 江戸川病院心臓血管外科
趣味:広島県出身なのでカープファン、ファンと言うよりカープは僕の血です。広島県民にとってカープは血液みたいなものです。他には体力づくりも兼ねて登山もしたりします。
山岡理事長 インタビュー(前編)

訪問診療に対して、実は最初はネガティブでした
–さいたま北クリニックの開院から2年半が経ちますが、訪問診療のこれまでとこれから展望をお聞かせ頂けますか。
それを語るのであれば、まず訪問診療をする前、やり始め、今という形の方が説明がいいです。
まず、訪問診療を行う前なので、元々病院にいた時です。病院にいた時はあんまり訪問診療に対して良いイメージを実は持ってなかったです。
どういうイメージかと言うと、なんとなく、その場で出来るお薬を出されているようなイメージがあったので、自分としては病院に勤めている時代の時は、「かかりつけが自分である以上は、僕の方に来てほしいな」と患者さんには思っていました。責任持ってしっかり診てくれるという形で思っていました。これが訪問診療に入る前です。
訪問診療は革新の時期へ
–ネガティブだったんですね。
ネガティブでした。
それは、ただ単に後ろ向きというわけではなく、訪問診療をやってみて、今やっている形の医療でいいのかなと、疑問から来る感情でした。
訪問診療という医療の革新。
これが必要なのではないかと。私が今まで心臓血管外科医として20年間、真摯に患者さんと向き合っていた医療を訪問診療で再現できないかなと日々考えていました。
要するに、「自分の20年間の医療をそのまま活かせるような診療ができないかな」という想いがあって、それを訪問診療でやろうと。なので、私は最初「訪問診療医」というカテゴリーではなくて、自分のことを「心臓外科医」と思って地域医療に携わる心構えをしました。心臓外科医としてやっていた医療をそのまま地域医療の枠組みに当てはめるようにやってきたというのがやり始めになります。
–心臓外科医として携わる、とはその考え方を教えて下さい。
心臓外科医としてやってきた医療理念をそのまま地域医療に当てはめてやってきたということです。
その理念というのが一番大事なところなんですけど、困っている人に自分に何ができるのだろうというのをしっかり考えて、行動を起こすということの繰り返しです。これは心臓外科医時代からやっていることなんですけど、とにかく困っている方に自分として何ができるんだろうということをしっかり考えて、何をすべきだろうとか、そういうことをしっかり考えて行動に移してきた。
そんな2年半だったと思います。


「自分の人生で良かった」そう思ってもらえるように-最期まで諦めないこと
–その医療理念を達成するために行動してきたこととは。
1番は傾聴力であったり、しっかり寄り添いながら、最期まで諦めないという私たちの思いとスキルです。
諦めないというのは訪問診療に携わると、終末期の方が多いので。終末期における「最期まで諦めない」というのは、尊厳を持って生きることを意味します。
その方が最後まで自分の人生を過ごして、心からよかったなと思えるような。私たちがその気持ちを万全な環境でケアし続ける対応力とスピード感は常に意識しています。
–終末期医療において、「最期まで諦めない」という考えは、多くの患者やその家族にとって大切なテーマです。
はい。終末期であっても、症状緩和やQOL(生活の質)向上を目指す治療やケアは続けられます。たとえば、痛みや呼吸困難の緩和、栄養や水分補給、精神的なサポートなどがこれに当たります。
また、最新の治療法や薬が利用可能な場合、そうした選択肢を模索することも「諦めない」姿勢の一つです。
とはいえ、終末期において、患者さん本人がどのような人生の最期を望むのかが重要です。延命治療を希望する患者さんもいれば、自然な経過を大切にし、延命措置を避けたいと考える患者さんもいます。どちらの選択でも、「最期まで諦めない」という意味はあり、本人の意思を尊重したケアが必要です。
ご家族にとっても終末期の患者を見守ることは非常に辛い経験ですが、希望を持ち続けることや、少しでも良い状態を保つために努力を続けることが「諦めない」という考え方になります。また、患者との時間を大切にし、感謝や愛情を伝えることも重要です。
みんなが最期に笑顔でいられることを一番に。
–「自分の人生で良かった」ご家族の方も嬉しいのではないかなと思います。
「ありがとうございます」と声かけられる方が圧倒的に多いです。自分の客観的な評価は、なかなか難しいのですが…。
例えば、その方が最終的に亡くなる時に「自分の人生は良かった」と言うわけではないので、最期に家族の方であったり、みんなが最後に笑顔でいられる環境を作る。
その上で「悲しいけど、いい人生だったね」と思っていただけることも私たちの仕事と思っています。
–診療も大切ですが、看取りも重要な使命のような気がします。
終末期の方のご家族も含めて、みんな笑顔で最期に送り出せるような環境をしっかり作ってあげるということが大事かなと思ってやっています。
私のイメージでは、お通夜があるじゃないですか。お通夜って故人を囲って、みんなでワイワイガヤガヤ思い出話に花を咲かせたり、湿っぽさもあるかもしれませんが、そうじゃなくて、あの時の思い出話をしたり「あの時はこうだったよな」と言って故人を偲ぶじゃないですけど。そういう思い出話ができる雰囲気が、医療の中にあってもいいかなと思って。
私自身も数ヶ月という短い期間でしか会ってないかもしれないけど、その数ヶ月でその人の人生をたくさん知れる努力を、いろんなことが書いてある情報を元に、その方が過去どういう方だったのかというのをしっかり理解した上で、ご家族とその情報を共有しています。
そこに本当に今までずっと寄り添っていた形でいれるように、自分自身もそこに気持ちを持っていって、最期の看取りまでご家族全員とそこに携わっている感覚。
こういった感覚を看護師、メディカルサポーターなどのスタッフ全員で共有して、本当にお通夜のような温かい雰囲気でも持っていくような形にはしています。